現在、物流業界は人手不足であり、多くの人材が求められています。
しかしそのような状況でも、「未経験でも転職できるのか?」と不安に思う方もいるでしょう。
実際のところ、物流倉庫作業では特別な知識やスキルが必要ないため、未経験でも十分に転職可能です。
この記事では、未経験でも物流倉庫で働ける理由や具体的な仕事内容、メリット・デメリットについて解説します。
本記事を読めば、物流倉庫での仕事の流れや自分に適しているかどうかのヒントを得られます。
未経験から物流倉庫への転職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
物流倉庫作業は未経験でも大丈夫!
物流倉庫の転職は未経験でも問題ありません。
実際、異業種から転職して活躍している方も多くいます。
とくに、長年別の職種で働いた後、30代・40代で物流倉庫へ転職し新たなキャリアを築いている方も少なくありません。
ここでは、未経験でも物流倉庫作業を始めやすい理由について説明していきます。
特別な知識は必要ない
物流倉庫作業で働くにあたって、特別な知識やスキルは必要ありません。
そのため、未経験からでも挑戦しやすい仕事です。
しかし、業務の多くは長時間の立ち作業や荷物の運搬を行うため、一定の体力は求められます。
例えば、次のような場面があります。
- 20キロ以上の荷物を運んだり積み上げたりする作業がある
- 倉庫内を1日中歩き回る必要がある
- 立ったまま作業し続けることが多い
このように、物流倉庫では知識やスキルは必要なくても、それなりの体力は必要です。
しかしこれらの業務も続けるうちに慣れてくるため、未経験でも十分に始められるでしょう。
フォークリフト免許はなくても大丈夫
物流倉庫の仕事と聞くと、「フォークリフトの免許が必要では?」と考える方も少なくないでしょう。
しかし、フォークリフト免許がなくても就職できる企業はあります。
その理由は、以下の通りです。
- フォークリフトを使用しない業務もあるため
- 免許は入社後に取得すればよいため
物流倉庫には、フォークリフトでの荷物の運搬以外にもさまざまな業務があります。
そのため、入社時に免許を持っていなくても問題ありません。
また、企業によってはフォークリフト免許取得のサポートをしているところもあります。
入社後に業務を通じてフォークリフトの操作方法を学び、慣れてから免許を取得できる制度を設けている企業もあります。
そのため、免許がなくても安心して始められるのがメリットです。
仕事内容
それでは、主な仕事内容について見ていきましょう。
物流倉庫での業務は多岐にわたりますが、基本的にシンプルで未経験でも始めやすいものがほとんどです。
業務ごとに役割が分かれているため、それぞれの作業を理解しながら取り組むことが大切です。
仕事内容
- 入荷
- 入庫
- ピッキング
- 仕分け
- 検品
- 梱包
- ラップ巻き
- ラベル貼り
- 積み込み
以下に、それぞれ1つずつ説明します。
入荷

「入荷」とは、倉庫に届いた荷物を受け入れることを指し、この業務を「荷受け」と呼んでいます。
荷受けをする際は、いずれの方法でも「パレット」を用います。
パレットとは、正方形や長方形の形をした木製やプラスティック製の荷台のことです。
パレットのイメージは以下の通りです。
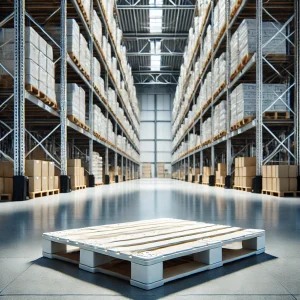
荷受けは以下の手順で行います。
- ドライバーが持参する伝票と、倉庫側の入荷リストを照合し荷物の種類や数が合っているかを確認する
- トラックに積まれている荷物をパレットに載せる
- 実際に積んだ荷物の種類や数が合っているか、また破損がないかを確認する
- パレットに積んだ荷物をフォークリフトで運ぶ
荷物はパレットに載っている場合とそうでないケースがあります。
ポイント
✅パレットに積まれている場合
フォークリフトでそのまま運ぶ
❌パレットに積まれていない場合
人の手で荷物をパレットに移し替える必要がある
荷物をパレットに移す際は、荷崩れしないように積むのがポイントです。
また、パレットの規定の高さまで積むのが一般的です。
積み終わった荷物は、フォークリフトを使用して倉庫内に運びます。
入庫(格納)

荷受けした荷物を棚やラックに入れることを入庫(格納)と言います。
「入荷」や「入庫」と聞くと、混同される方もいるでしょう。
「入庫」は「入荷」から検品を通じて棚やラックに格納することを指します。
倉庫内には、荷物を保管するために棚が置かれていることが一般的です。
ピッキング作業

ピッキングとは、倉庫に保管された商品を必要な分だけ取り出し、出荷場所へ集める作業のことです。
必要な商品やその数は、出荷指示書(ピッキングリスト)に記載されています。
ピッキングは以下の流れで行います。
- 出荷リストを確認する
- 指定されたロケーションへ移動する
- 商品を取り出す
- カートやパレットに積み込む
- ピッキングリストと照合する
- 出荷場所へ運ぶ
「ロケーション」とは、商品の位置情報のことです。
必要な商品の保管場所は、このロケーションを見れば分かります。
例えば、ピッキングリストに「A-03-1」と書かれていたとしましょう。
この場合、それぞれの意味は以下のようになります。
- A:倉庫内のエリア
- 03:棚の番号
- 1:棚の段数
このように、ロケーション番号を使うことで、倉庫内のどこに商品があるのかを把握できます。
また、ピッキング時には、カートやパレットを使用して商品を運ぶのが一般的です。
状況に応じて、以下のように使い分けると良いでしょう。
| カートを使用する場合 | パレットを使用する場合 |
| 小型の商品や軽量の荷物を運ぶとき
少量のピッキングを行うとき 狭い通路での作業が必要なとき |
重量のある荷物を運ぶとき
大量の商品をまとめて運ぶとき フォークリフトを使って移動させるとき |
商品を集め終わったら、再度ピッキングリストと照らし合わせて間違いないかを確認することが重要です。
少しの確認がで重大なミスを防げます。
仕分け作業

仕分け作業とは、混在された商品を種類ごと、または出荷別ごとに分ける業務です。
仕分けには、人の手で行う「手仕分け」と機械による「自動仕分け」の2つの方法があります。
両者は、基本的には同じ流れで行われます。
仕分けが必要なときは、主に以下の2パターンです。
- 入荷時
- 出荷時
どちらの場合も基本的な仕分けの流れは同じです。
仕分け作業の例
1つのパレットにA、B、Cという3種類の商品が混在している
1.商品ごとに分ける場合
・別のパレットを3枚用意し、Aの商品はA専用のパレット、BとCもそれぞれ専用のパレットに分ける
2.出荷先ごとに分ける場合
・A社向けの荷物は1つのパレットにまとめ、B社、C社向けの商品もそれぞれ分ける
このように、仕分け作業は難しい作業ではありませんが、正確な出荷や効率的な管理のために必要な工程です。
検品作業

検品作業とは、商品の状態や数量に過不足がないかを確認する業務です。
検品作業は、基本的に以下の2つに分かれます。
- 入荷検品:倉庫に届いた商品のチェック
- 出荷検品:出荷前の商品のチェック
どちらの作業の流れは基本的に同じですが、入荷検品は仕入れ商品の確認、出荷検品は顧客に届ける荷物の最終チェックに当たります。
検品作業が必要な理由は、以下の通りです。
- 製造時の不良や運搬・積み下ろしの際の破損などにより、出荷できない状態の商品が含まれている可能性があるため
- 発送元が出荷数を誤ったり、異なる商品を送ってしまったりする可能性があるため
このように、不良品や数量の不足は、クレームや返品の原因となり、企業の信用を低下させます。
そのため、検品の精度は顧客満足度に直結し、取引先との信頼関係を築くために欠かせない工程です。
梱包作業

梱包作業とは、顧客に出荷する商品を傷つけないよう、段ボールや緩衝材を使って放送する工程です。
商品は基本的にトラックで輸送されるため、配送中に衝撃を与える可能性があります。
しかし適切に梱包することで、商品の安全な状態で顧客へ届けられます。
梱包の手順は以下の通りです。
- 梱包資材(段ボール)を用意する
- 緩衝材を用意する
- テープカッターなどを使用して、段ボールの底面をしっかりと閉じる
- 必要な商品を箱に詰め、適切な量の緩衝材を入れる
- 段ボールの天面をテープで固定し、しっかり封をする
テープカッターを使用することで、作業効率を上げられます。
慣れないうちは、扱いが難しく感じるでしょう。
しかし、作業を繰り返すうちにスムーズに使えるようになってきます。
ラップ巻き作業

ラップ巻きとは、「ストレッチフィルム」という透明なフィルムをパレットに積んだ荷物に巻き付ける工程です。
ラップ巻きの目的は、搬送中の荷物を崩れないように固定することです。
「ラップ」と聞くと、家庭用のサランラップをイメージする方もいるでしょう。
しかし、物流で使用されるストレッチフィルムは家庭用とは異なり幅が50㎝あり、強度が高く伸縮性があるのが特徴です。
ストレッチフィルムのイメージは以下の通りです。

ラップ巻きの手順は以下に説明します。
- 適量のラップを引き出し、先端を丸める
- 丸めた先端を積まれた荷物の間に差し込む
- 下から上にらせん状に巻いていく
- 2周ほど巻き、適度な強さで荷物を固定する
- 巻き終わったら、手でちぎるか、荷物の角で切る
注意すべき点は、荷物全体にストレッチフィルムがかかるように巻くことです。
巻かれていない部分があると、搬送中に荷崩れが生じ、商品が破損する恐れがあります。
商品の安全性を確保するためにも、巻き終わった後にしっかりと確認を行うことが重要です。
ラベル貼り

ラベル貼りとは、出荷先や商品の情報が書かれたラベルを商品に貼る工程です。
ラベルを貼ることによって、商品の保管や出荷ミスを未然に防げます。
ラベル貼りの目的は以下の通りです。
✅正確な配送
- ラベルに記載された情報をもとに、適切な配送先へ確実に出荷できる
- 宛先の間違いやご配送を防げる
✅在庫管理の効率化
- ラベルに書かれた情報をスキャンすることで、商品のロケーションが分かる
- 倉庫内でのピッキング作業を効率化できる
ラベル張りはシンプルな作業ですが、物流業務の効率化に欠かせない業務です。
積み込み作業

積み込み作業とは、出荷業務の最終工程にあたり、商品をトラックに積み込む業務です。
積み込み作業の手順は、入荷業務と同様で以下の通りです。
- 人の手で商品をトラックに積み込む
- フォークリフトでパレットに載った商品をトラックに積み込む
商品をトラックに積む際の注意点は、重いものを下に配置し、荷物の間に隙間ができないようにすることです。
こうすることで、荷物の破損や荷崩れを防げるからです。
倉庫内作業はどういう人に向いているか
ここまで作業内容について解説してきましたが、倉庫内作業はどういう人に向いているのでしょうか。
ここでは、倉庫内作業に向いている人の特徴について説明します。
集中力が高い人
黙々と作業をこなせる人
体力に自信がある人
以下に、それぞれ1つずつ解説します。
集中力が高い人
倉庫内作業では、商品を間違えずに正確かつ安全に取り扱うことが求められます。
そのため、効率よく作業を進めていくには集中力が必要です。
例えば、ピッキング時に間違った商品や数量を取り出してしまうとご出荷になり、顧客からのクレームの原因になりかねます。
また、検品作業では、商品の状態や数量に間違いないかを細かくチェックしなければなりません。
このように、物流倉庫ではミスが許されない業務が多いため、注意力を持続できる人に向いていると言えるでしょう。
黙々と作業をこなせる人
物流倉庫では、基本的に1人で作業する場面が多いため、黙々と作業をこなせる人に向いています。
必要最低限のコミュニケーションは発生しますが、接客業のように頻繁に会話をする必要はありません。
そのため、人と話すのがあまり得意でない方も問題ありません。
自分のペースで作業を進めたい方に適した職種だと言えるでしょう。
体力に自身がある人
倉庫内での作業では、重量物を取り扱ったり、長時間立ちっぱなしでの作業を行うことが多いため、一定の体力が求められます。
企業によっては、20~30キロほどの荷物を扱うこともあり、持ち上げたり運搬したりする作業が発生します。
とくに、積み込み作業では頻繁に荷物を持ち運ぶため、筋力や持久力が必要不可欠です。
倉庫内作業は難しい作業がなく、コツをつかめば効率的に動けるようになります。
しかし、ある程度の体力がなければ長く続けていくのは難しいでしょう。
倉庫内で働くにあたってのメリット
ここでは、倉庫内で働くにあたってのメリットについて説明します。
- 特別な知識が不要
- フォークリフト免許取得支援がある企業もある
- 自分のペースで取り組める
以下に、それぞれ1つずつ解説します。
特別な知識が不要
倉庫内で働くにあたって、特別な知識や専門的なスキルは必用ありません。
シンプルな作業がほとんどであるため、一度覚えてしまえばすぐに慣れるからです。
例えば、ピッキングやラップ巻きはある程度の体力が求められますが、作業そのものは難しくありません。
そのため、未経験からでも十分に始められるのがメリットです。
フォークリフト免許取得支援がある企業もある
会社によれば、フォークリフト免許の取得支援を行っているところもあります。
フォークリフト免許取得には、受講費用や講習にかかる時間が必要です。
しかし支援制度を利用すれば、自己負担を抑えつつ、スムーズに免許を取得できます。
例えば、会社が免許取得費用を全額負担し、講習期間が出勤扱いになるケースもあります。
このような制度があれば、自己負担なしで免許の取得が可能です。
フォークリフトの免許を取得すれば、業務の幅が広がり、昇給のチャンスも期待できます。
自分のペースで取り組める
倉庫内作業は、基本的に1人で仕事をこなすことが多いため、自分のペースで取り組めます。
とくに、ピッキング作業では決められた指示に従って作業を進めていけば問題ありません。
そのため、無理に周囲の人にペースを合わせる必要はありません。
また、接客業のように常に人と話す必要がないため、集中して作業ができます。
倉庫内で働くにあたってのデメリット
倉庫内作業は簡単な業務が多く始められやすい業務ですが、デメリットも存在します。
ここでは、倉庫内で働くにあたってのデメリットについて説明します。
体力的にきつい
空調などの設備有無
不規則な勤務シフト
以下に、それぞれ1つずつ解説します。
体力的にきつい
倉庫内作業は簡単なものが多いですが、体力的にはきつい仕事と言えます。
重量物を持ち運んだり、長時間立ちっぱなしの作業を行うため、身体への負担がかかります。
例えば、
- 積み込み作業では重い荷物を何度も持ち上げる必要があるため、腕や腰を痛めることがある
- ピッキング作業では、長時間歩き回る必要があるため、足腰に負担がかかる
このように、作業自体は単純で覚えやすいのですが、身体への負担は決して軽くありません。
そのため、倉庫内作業を検討している方は、自分の体力と業務内容を確認することをおすすめします。
空調などの設備有無
倉庫によっては空調設備が整っていない職場があります。
そのため、夏場は暑く、冬場は寒い環境で作業をしなければなりません。
空調がない職場で働く際のリスク
- 夏場は蒸し暑く、熱中症がリスクが高まる
- 冬場は冷え込みが厳しく、体調を崩しやすい
このように、空調設備がない倉庫では、体調への影響が大きくなります。
そのため、作業中は体調管理を徹底することが大切です。
不規則な勤務シフト
企業によっては、日勤のみならず2交代制や3交代制のシフトを運営している企業もあります。
その理由は、日勤のみでは生産性に限界があり、需要に十分対応できないためです。
例えば、大手物流企業では、24時間体制で商品を取り扱う必要があるため、2交代制や3交代制を導入しています。
そのため、シフトによっては午後からの出勤の日もあるでしょう。
その場合、朝はゆっくりできますが、夜勤のシフトもあるため生活リズムが乱れます。
深夜手当がつくメリットはありますが、不規則な生活により、体調を崩しやすくなるのはデメリットと言えます。
まとめ
この記事では、物流倉庫への転職を検討している方に向けて、仕事内容やメリット・デメリットについて解説してきました。
倉庫内作業は一定の体力が必要ですが、特別な知識や専門的なスキルは不要です。
多くの業務はシンプルで覚えやすく、未経験からでも始めやすい仕事です。
また、フォークリフト免許の取得をサポートしている企業もあり、働きながら資格を得られるチャンスもあります。
これから物流倉庫で働いてみたいと思っている方は、転職を検討してみてはいかがでしょうか。
本記事が物流倉庫への転職を考えている方の参考になれば幸いです。
